-
論文
育成者権の活用と海外ライセンス
~海外ライセンス指針も踏まえて~
昨今、育成者権や商標権を海外のパートナー企業等(ライセンシー)にライセンスし、現地で果実等の生産および販売に取り組む事例が海外市場を開拓する方法として注目を集めています。令和5年12月には農林水産省が「海外ライセンス指針」を公表し、海外のパートナー等にライセンスを行う場合の戦略や考え方が明らかにされました。本稿では、このような海外ライセンスを行う際の契約上のポイントを解説します。
ライセンシングの内容
(1)ライセンスの在り方
これらの例からも分かるとおり、ライセンスの内容はさまざまであり、育成者権のライセンスのみを行っている事例、商標権のライセンスのみを行っている事例、また両方を組み合わせたり、ノウハウのライセンスも合わせて行っているケースも存在する。
ライセンスモデルもさまざまであるが、前述の海外ライセンス指針においては、以下の2つの大きなモデルが紹介されている。
①種苗業者、収穫物生産者、流通業者のそれぞれにライセンスするモデル(以下、モデルA)
②流通業者にライセンスし当該流通業者が種苗増殖、収穫物生産をサブライセンスするモデル(以下、モデルB)
いずれのモデルも、種苗の販売先、収穫物の販売先を契約により特定することで、生産・流通を管理するとのことであるが、モデルAでは、日本のライセンサーが生産・流通・販売を担う海外の事業者と個別に契約を締結して管理する必要があるため、実際はハードルが高いとも思われる。そのため、種苗生産や収穫物の生産・販売を自社で担えるか、またはそれらのネットワークを有する流通業者等にライセンスをするモデルBがまずは取り組みやすいと考えられる。なお、モデルAとモデルB以外のライセンスの在り方が存在しないというわけではなく、実際に海外ではさまざまな事例がある。詳細は、農林水産省の委託事業の報告書が参考になるため、参照されたい(注3)。
(2)ライセンス契約
以下では果樹品種の育成者権のライセンスを行う場合を念頭において検討する。
果樹品種のライセンスを行う場合の契約を大別すると、試験栽培フェーズと商業化フェーズの2つのフェーズが主に挙げられる(便宜上、試験栽培もライセンスの類型に含める)。
(ア)試験栽培契約
育成者権の商業的なライセンスを行う前提として、まずは対象となる品種が現地の気候風土に適しているかどうかといったことをテスト等により確認する必要がある(その結果を品種登録出願の際のデータとして用いるという意義もある)。そのため、育成者権の商業的なライセンスの前に、試験栽培を行うための契約を締結することが考えられる。試験栽培は品種登録出願ないし品種登録に先立ち行われることが主に想定され、当該試験栽培に係る契約においては、現地での試験栽培の実施から品種登録出願・品種登録のサポートまでをスコープに入れることがあり得る。試験栽培契約の主たる目的は、ライセンスの候補となる品種の現地における適応性等の確認であるため、試験栽培の委託および受託者から委託者への試験結果の報告が契約内容の中核となる。
かかる試験栽培契約に際しては、委託者から受託者に対して種苗の提供が行われるところ、種苗の所有権を移転する必要はないため、育成者権の消尽や新規性喪失の問題を理論的には回避することができる。しかし、受託者から種苗が無断譲渡されるなどの品種流出のリスクがあることから、受託者は信頼できる者を選定しなければならない。また、受託者には種苗の管理を徹底させ、契約上も種苗の無断譲渡等を禁止しておく必要がある。加えて、試験栽培の受託者が商業的なライセンス契約のライセンシー候補でもある場合には、品種登録出願の代理も受託者が実施する形とし、仮に品種登録が奏功した際には、当該受託者に、許諾対象地域における登録品種の商業化に係る育成者権の独占的ライセンシーとなり得るオプションを与えるといったことも考えられる。
具体的な条項はケース・バイ・ケースであるが、検討対象となる条項の例としては、以下のものが想定される(各国の法制度によって異なる条項を規定すべき場合があり得ること、また、以下の条項が網羅的ではないことに留意されたい)。
①スケジュールどおりに試験栽培を進捗させるために、試験栽培計画書を定めたうえ、当初計画したタイムラインどおりに実施されなかった場合(試験栽培の不奏功が見込まれる場合)には委託者の判断で解約できるようにする条項。
②新規性喪失防止の観点から、試験用苗木の利用は試験栽培目的に限られることを明確にする条項。なお、新規性喪失を防ぐために、試験用苗木および関連する植物体に係る所有権は委託者に留保され、所有権移転しないことを明確にしておくことも考えられる。ただし、どのような場合に新規性を喪失するのかについては、各国の法制度によって差異があるため、各国の制度に応じた対応を検討する必要がある。
③試験用苗木の無断譲渡を抑止する観点から、譲渡禁止および違反した場合のペナルティーを定める条項。
④試験栽培においてEDV(従属品種)を含む新たな植物品種が生じた場合の知的財産権を確保するために、試験対象品種の変種・突然変異に係る知的財産権が委託者に帰属することを明確にする条項を規定することが考えられる。なお、当該規定が各国の競争法に抵触しないかは別途検討を要すると思われる。
⑤国によっては、土地の所有者との間で樹木の所有権を留保する旨の合意がない場合には、樹木の所有権は植栽した土地の所有者に自動的に帰属する(付合する)ことがあり得る。したがって、土地の譲渡により、許諾対象品種の樹木の所有権が土地の新所有者に取得されてしまうリスクへの対応として、農地の譲渡に先立ちライセンサーに対する通知を義務付け、さらに、農地の新取得者との間で樹木に係る所有権の帰属について合意できない場合には、樹木の伐採・撤去を義務付ける条項等を設けることが考えられる。
⑥試験栽培期間中の試験対象品種の管理状況を確認できるよう委託者の立入権・監査権を定める条項。
⑦契約が終了した場合には、試験場に所在する試験用苗木・収穫物等の撤去、除却を義務付ける条項。
(イ)商業化フェーズのライセンス契約
試験栽培を通して現地での適応性等が確認できた場合には、商業化に関するライセンス契約に進む。契約内容は、ライセンシー候補がどのような業務を実施できるか(苗木・収穫物生産、流通、販売に関してどのような業務を行う能力を有しているか)、どの程度信頼して任せることができるかといった条件により左右されるが、本稿では前述のモデルBを前提にする。
モデルBは苗木流出時の侵害対応等の面でメリットがある。すなわち、侵害状況の確認、証拠収集および侵害対応を現地パートナー(マスターライセンシー)に委ねる契約内容にしておけば、これらの対応を任せることができるため、エンフォースメントの観点でも優れている(サブライセンス先の苗木業者等が契約違反をした場合、マスターライセンシーの契約違反とみなされる条項を規定しておけば、マスターライセンシーへの責任追及もなし得る)。
検討対象となる条項の例としては、以下のものが想定される(網羅的ではないこと等については試験栽培契約と同様である)。なお、試験栽培契約と重複する内容については省略する。
①許諾対象地域において、許諾対象品種を生産・販売することができるライセンスを付与する条項。仮に独占的なライセンスとする場合、ライセンサーは許諾対象地域において、ライセンシー以外の第三者に同じ許諾対象品種をライセンスして収益を得ることができなくなり、ライセンシーの生産・販売パフォーマンスが悪いと、ライセンサーの利益が損なわれるおそれ(許諾対象品種を塩漬けにされてしまうリスク)があるため、生産量・販売額に連動しない形でのミニマムのロイヤルティー支払義務を定めることもあり得る。
②現地のマスターライセンシーがサブライセンス先である苗木業者、生産者、包装業者、販売業者の選定・管理を行う条項。
③日本産の許諾対象品種との競合可能性が高い国・地域への出荷を防止するため、ライセンサーがあらかじめ指定する国・地域への無断輸出を制限する条項。
④ロイヤルティーについての別の観点として、苗木のみを金額の算定要素とするのではなく、収穫量・栽培面積等も算定要素とし、収穫・販売が行われる間の長期にわたりロイヤルティーを得られる条項とする。
⑤ライセンシーにおける許諾対象品種の生産管理・品質管理状況やロイヤルティーの計算の基礎となる書類・データを確認できるようにするため、ライセンサーの立入権・監査権を認める条項。
(3)商標権のライセンス
商標権のライセンスも合わせて行う場合、ブランド管理の観点から許諾対象商標を付することのできる収穫物の品質をコントロールする必要がある。そこで、商標の使用が認められる収穫物の規格や品質管理についての基準はライセンサーが定めることができる条項等を設けることも一考に値する。
加えて、育成者権存続期間満了後も継続してロイヤルティーを確保する方策として、商標権のライセンス契約を存続させて、苗木または収穫物への商標使用の対価としてライセンシーからロイヤルティーを収受することも考え得る。なお、国によっては、育成者権の存続期間満了後も引き続き同権利に関連するロイヤルティーとして支払義務を課すと、権利の濫用等として、競争法上の疑義が生じる可能性がある点には注意を要する。



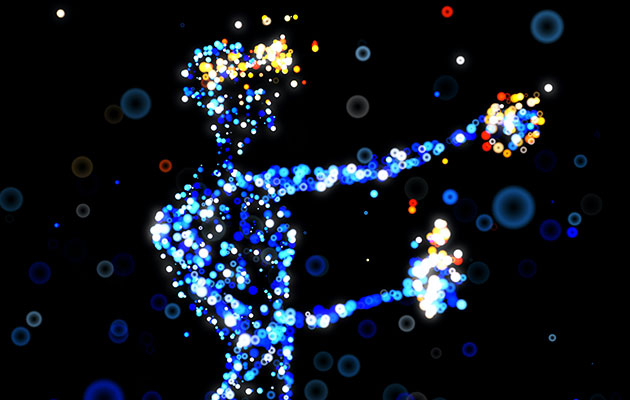


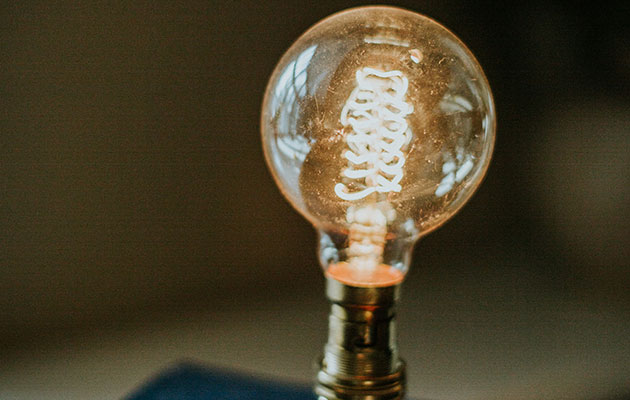


農林水産省における勤務経験を活かして、農林水産業・食品分野の規制対応、政策提言・ルールメイキング、新規事業・事業展開のアドバイス、契約関係のサポートを幅広く行っている。
M&A・ジョイントベンチャーや事業承継、スタートアップの資金調達、知財戦略、国際取引等についての戦略的サポートも手がける。
アグリフードプラクティスの活動については、FT Innovative Lawyers Asia-Pacific Awards 2023において革新的な活動が評価され”Commended”に選出された。